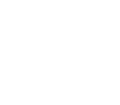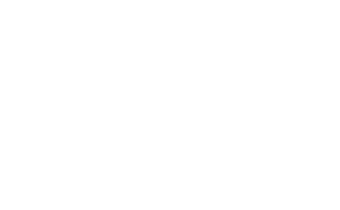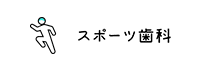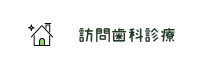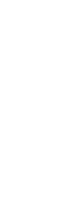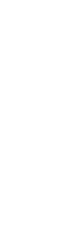子どもへのレントゲンの影響が気になります。

小児歯科ブログ
プルチーノデンタルクリニックです。
歯医者に行くと、ほぼ必ず撮影されると言ってもいいくらい、皆さんレントゲン撮影の経験があると思います。しかし、子どものうちはあまり撮ってほしくない、うちの子にはレントゲンは早いからまだ必要ないと保護者の方が決めつけてしまうことがあります。我が子を大事に思えばこその行動ですが、残念ながら逆の効果になってしまうこともあります。歯医者も保護者の同意がなければ検査をすることはできません。そこで、なぜ子供でも歯医者はレントゲンを撮ろうとするのか。どんなことをチェックしているのか。その撮影した影響はどれくらいあるのか、そんな疑問にお答えしていきます。
レントゲンの被爆量ってどれくらい?
レントゲン撮影は放射線を使っているので控えたいという心理があると思います。では実際、検査に必要な放射線量はどれくらいなのでしょう。歯科でのレントゲン検査は全体を2次元的に再構築した「パノラマレントゲン」と、ある一部分のみを撮影する「デンタルレントゲン」があります。パノラマレントゲンは一度の撮影で歯はもちろん副鼻腔と呼ばれる上顎洞や下顎の骨も撮影が可能です。反対にデンタルレントゲンは狭い範囲ながらむし歯はもちろん、歯と骨の間に存在しているわずかな歯根膜腔の状態も把握するのに有効で、細かく調べたい時に力を発揮します。広範囲を撮影するパノラマレントゲンでも被爆量は0.01mSvと言われています。この数字をもう少しわかりやすくすると、私たちが日本で過ごしている中で一人あたり年間に2.1mSvnの自然放射線を受けていると言われています。つまり、パノラマレントゲンは自然に浴びている量と比較しても200分の1程度で、デンタルレントゲンにいたっては1回の放射線量は0.008mSvですからごくごく微量な数字だと分かります。そのうえ、小児のレントゲン撮影時には少ない放射線量で撮影できるように小児用の設定がどのメーカーでもされていますので実際の被爆量はさらに少ないものです。これらは技術の進歩により被爆量の減少を実現してきた結果ですので、先の未来ではさらに低減化されていくことも期待できます。ちなみに東京からニューヨークを飛行機で往復した際に空から受ける被爆量は約0.2mSvだそうです。この数字からもいかに現在のレントゲン検査の被爆量が少ないかわかります。
レントゲン撮影はメリットとデメリットとを天秤にかける
しかし、歯科でのレントゲン撮影時の放射線量が少ないと言ってもむやみやたらに撮影するわけではありません。なぜなら子どもは大人に比べて放射線の感受性が数倍高いと言われています。なので、デメリット(放射線の被爆)とメリット(得られる情報)とを比べ、最小の被爆量で最大の利益が得られるように私たちは心掛けています。ではどんなメリット(得られる情報)があるかご紹介します。
1.歯の本数に異常がないかどうか
余分にできてしまった歯を「過剰歯」と呼びますが、これが顎の中に存在していることが理由で、本来生えてくるはずの歯が出てこれなくなってしまうことがあります。適切なタイミングで抜歯が必要となる為、発見が遅れて他の歯に影響を与えてしまうことが考えられます。逆に数が少ない場合「先天性欠損歯」と呼びますが、永久歯がこれの場合、先行して生えている乳歯は生えかわらないので、より乳歯を大切にする必要があります。もし生えかわらないことを知っていればより一層、むし歯にさせられないと本人も家族も努力するはずです。
2.大人の歯が傾いて生えてこようとしていないか
「異所萌出」といって本来、歯が生えてくるコースからずれて生えてこようとすることがあります。どこかにひっかかってしまい生えてこれないケースや、生えてきてもすごく傾いていて歯並びが悪くなり見た目や清掃性に問題がでてくることがあります。これらも前もって分かっていれば心づもりができたり対応の準備がしっかりとできます。
3.誰も気づかない大きなむし歯は無いか
むし歯は全てが痛いわけではありません。またひどくなると神経が死んでしまい逆に治ってしまったかのように症状がなくなってしまうこともあります。大きくなったむし歯の影響は骨を溶かし、いずれ生えてくる永久歯へも及ぶこともあります。乳歯や生えたばかりの永久歯はむし歯になりやすく進行も早い特徴があるので、怪しい歯は放置するのではなく早めの検査をおすすめします。
治療の必要性の判断をしたり、その治療のタイミングを逃さないようにするにはやはりレントゲン撮影が必要な場合があります。お母さんも、お父さんも、かかりつけの歯医者さんも子どもがスムーズに永久歯へ生えかわることを望んでいるはずです。あまり最初からレントゲン撮影はしないと決めつけないで検査の必要性をかかりつけ医と相談の上、お役立てください。